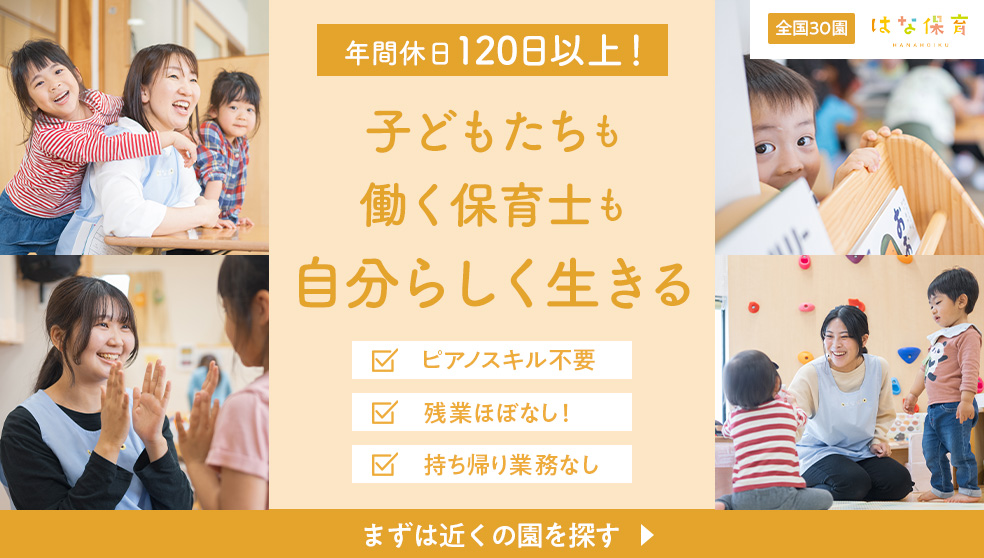保育士の新しい働き方を叶える「はな保育」が誇る透明性の高い経営
「保育園は公共性の高いサービスだからこそ、透明性と経営者としての責任感を」と力強く語る、「はな保育」の加藤義人代表。今までの保育業界の枠組みを見つめ直し、フラットで透明性の高い経営の姿を追求しています。その思いと取り組みについて聞きました。
最終更新日:2025.08.13
この記事は約 1未満 分で読み終わります。
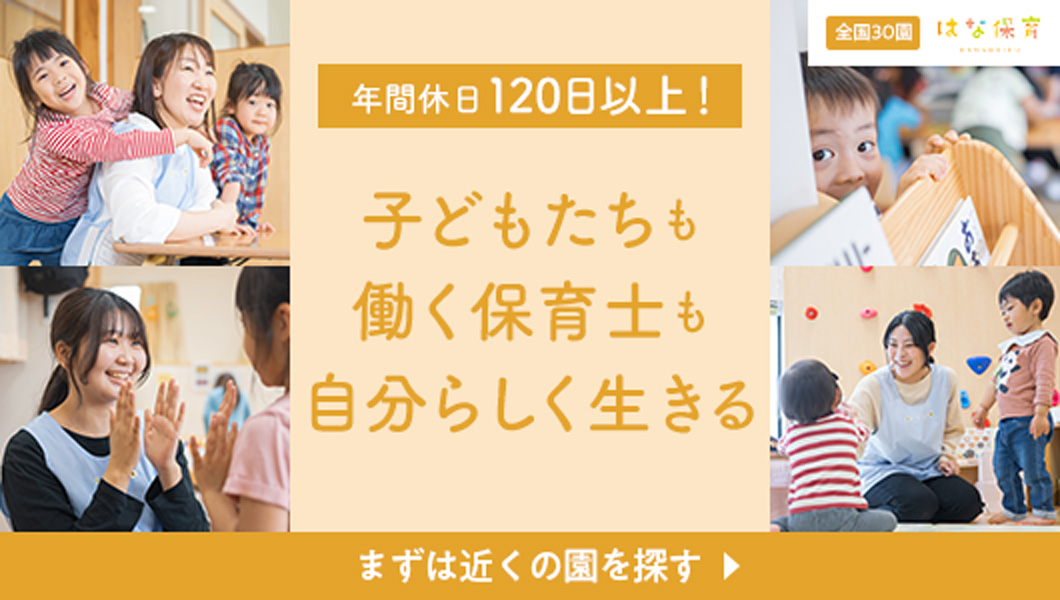
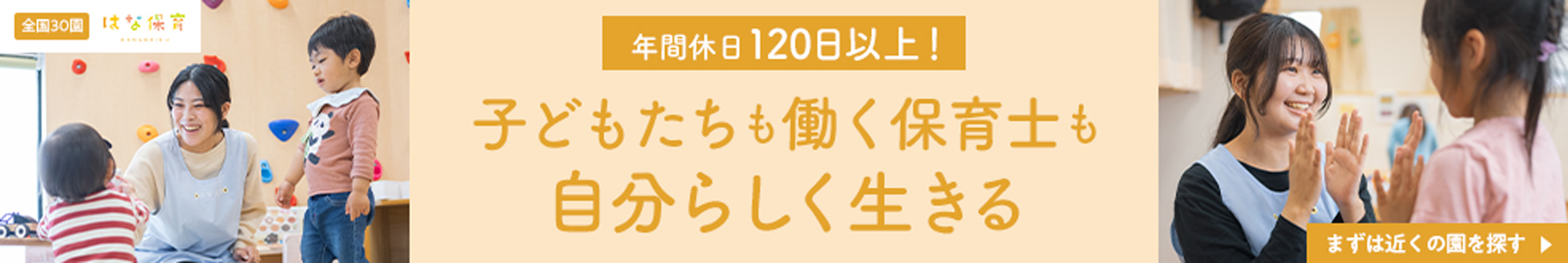
加藤義人(かとうよしひと)
株式会社はな保育 代表取締役社長。子どもも保育士も「自分らしく生きる」理念のもと、独自の保育環境と人材育成に力を注ぐ。現場の声を大切にした経営スタイルで、保育士の主体性を引き出し、業界に新たな可能性を示している。
株式会社はな保育は東海3県及び、関西地区に認可保育園、受託保育、児童発達支援など合計49施設を展開する会社です。保育の安定や様々なサービスの提供において職員が安定的に安心して仕事にまっすぐに向き合えることを大切に事業展開を行っています。子どもも保育士も一人ひとりの個性を尊重した環境づくりに取り組んでいます。有給取得率9割超、残業ほぼゼロなど、働きやすい環境が特徴です。
目次
保育園のあり方を見つめ直し、透明性の高い経営を
――保育業界の現状についてどのような思いを持っていますか?
保育園は公的資金で成り立っている事業です。業界全体として、その点への責任感や自覚がもう少し高まるといいなと感じています。例えば、保育園には「応諾義務」という、保護者が希望すれば原則として受け入れなければならない決まりがあります。ただ実際には、「両親が仕事の日でないと預かれません」といった運用や、発達に特性のあるお子さんの受け入れを躊躇するケースも見受けられます。
こうした状況は、本来の応諾義務の趣旨から外れているのではないかと感じることもあります。はな保育では、相談があれば基本的にすべて受け入れる方針を取っています。それは特別なことではなく、本来あるべき姿勢だと考えるからです。
また、保育士の給与体系についても私自身は課題を感じます。保育園は、行政の基準に準じて給与を決めることになっています。これは、給与への不満が出た際に「行政の基準だから仕方ない」と責任を回避しやすい仕組みに結果としてなっています。本来は、経営者が一人ひとりの働きを評価し、それに応じて給与を決定し、納得を得るのが経営の本筋だと私は考えています。
――そうした公正さや透明性を大切にする考え方は、はな保育の経営にどのように反映されていますか?
私たちの基本姿勢は「どこから見ても同じように見える経営」です。パートの方が見ても、正社員が見ても、同じように透明で公正な会社であるべきだと。特に現代はSNSなどで情報がすぐに広がる時代です。「業界の慣習だから」という理由だけで物事を判断することは、特に若い世代からすれば「ご都合主義」に映り、信頼を損なうことになりかねません。
こうした考え方は人事制度にも反映されています。給与面では、行政の定める範囲内ではありますが、賞与などについては本人の働きや貢献度に応じて差をつけています。有給休暇の取得率が9割を超えているのも、同じ考え方に基づいています。有給休暇は「もらうもの」ではなく、労働の対価として当然支払われるべきもの。入社後すぐに使える特別休暇を3日設けているのも、働き始めたばかりの方が休みを取りにくい状況を少しでも緩和したいという思いからです。
保育士が無理なく働くため、残業や持ち帰りを禁止

――従来の保育業界では、手作りの教材や園内装飾などに時間をかけることも多くありますね。
はな保育では、残業や持ち帰り仕事を原則として認めていません。勤務時間内に業務を終えられるよう、人員配置や仕事量を調整しています。
例えば、運動会のメダルを手作りするケースがあります。紙で作ったメダルと市販の金色に光るメダル、子どもたちが喜ぶのはどちらでしょうか。この場合、残念なことではありますが、金色の光るメダルを喜ぶ子どもたちが多いでしょう。手作りすることに意味があるケースももちろんありますが、時間と効率のバランスや経済性も考慮しながら、何が最も子どもたちのためになるかを本質的に見極める力が大切だと考えています。
誤解しないでほしいのですが、私たちはベテラン保育士のノウハウや頑張りを否定しているわけではありません。ただ、私たちが大切にしたいのは、時間をどこに使うのが最も子どもたちのためになるのかを常に考えることです。限られた時間の中で、子どもたちとの関わりを最優先にすることが、保育の本質だと考えるのです。
保育士のキャリアと成長を全力サポート
――保育士のキャリアへのサポート体制を教えて下さい。
はな保育では、保育士がライフステージに合わせて長く働けるよう、多彩で柔軟なキャリアパスを用意しています。現場での保育だけでなく、本社オフィスでの仕事に移ることもできますし、その逆も可能です。また、人間関係で悩んでいる場合は、無理に頑張ってもらうのではなく、別の園に異動できる制度も設けています。どんな職場でも人間関係の課題は起こりますから、環境を変えることで新たなスタートを切れるようにしています。
若い世代にはさらに積極的にキャリアアップに挑戦してほしいですね。20代だからといって園長をやれない理由はありません。手を挙げてくれれば、会社としてサポートしていく体制を整えています。最終的には「どんな業界でも通用する人材」を育てることが、はな保育にとっても、保育士本人にとっても、そして業界全体にとっても良いことだと考えています。
上場で透明性をさらに追求

――2023年4月には、東京プロマーケットへの上場を果たしました。
上場の大きな目的の一つは、経営をより透明化し、誰でもチェックできる仕組みにするためです。上場企業となることで、株主や投資家などの第三者の目が入り、経営の透明性が高まるとともに、不正や問題を隠すことがより困難になるのです。
私たちは以前から、どんなに些細なことでも懸念のある案件はすべて自治体に報告し、判断を仰ぐという姿勢を貫いてきました。上場企業となることで、この姿勢をより強固なものにできると考えたのです。また、社会的な信用や認知度も高まり、私たちの理念や取り組みをより多くの方に知っていただく機会にもなります。
そして何より大切なのは、保育という公共性の高いサービスを提供する事業者として、常に社会からの監視の目があることを自覚し、その責任をまっとうすること。上場はそのための大切なステップだと考えています。
よりよい保育業界を目指して
――保育業界の未来についてお聞かせください。
保育の仕事は「聖職」と言われることもあります。それは子どもに対する深い愛情や責任感の表れでもありますが、一方で労働者としての権利意識や義務意識が薄れてしまうリスクもあります。保育業界は、労使間双方の法律意識が希薄になってしまっていると感じます。保育士がもっと自分の権利や労働環境について声を上げ経営者と対等に向き合うことが大切だと思いますし、労働者として自分たちのレベルを高める必要があるとも思っています。そうした動きが、業界全体の底上げにつながるのではないでしょうか。
保育業界はまだまだ変わっていける部分がたくさんあり、だからこそ大きな可能性を秘めていると思います。子どもが好きで保育士になったのに、それ以外の理由で離れていくのは本当にもったいないことです。適切な労働環境や条件を整え、保育士がより長く活躍できる業界にしていきたいと考えています。
まとめ
私たちはな保育が目指すのは、公平性と透明性を重視した新しい保育園の形です。経営者としての責任を果たし、保育士が働きやすい環境を整えることで、子どもたちにより良い保育を提供できると考えています。これからも質の高い経営と、保育士が安心して働ける環境づくりを続け、業界全体の発展に貢献していきます。